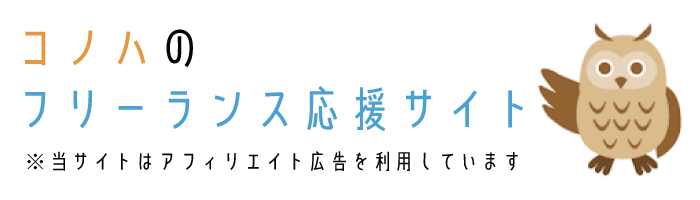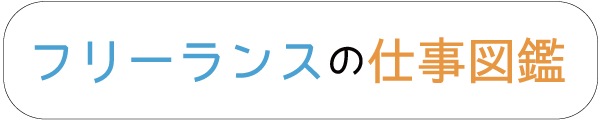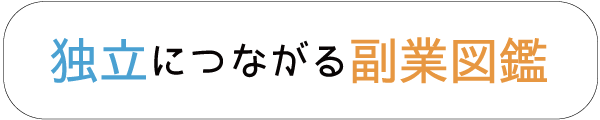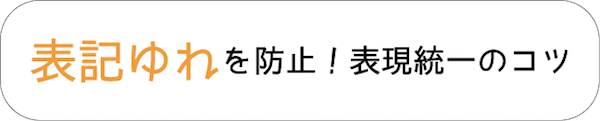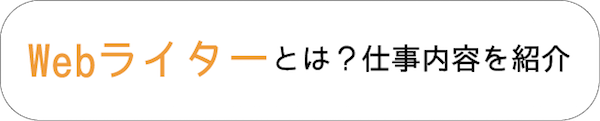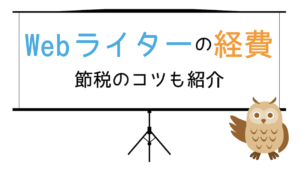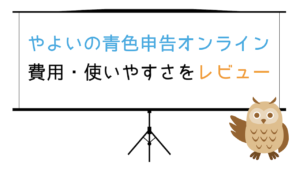日本語の文章は、「ですます調」と「である調」の2つに分けられます。
どちらの文体を使うかによって、文章全体の印象が大きく変わるため、メディアやターゲット層に合わせて選択することが重要です。
そこでこの記事では、
- 「ですます調」と「である調」の違い
- 「ですます調」と「である調」を使い分けるポイント
- 「ですます調」と「である調」は混在してもよいのか
といった内容について解説します。
例文を使ってわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
「ですます調」と「である調」の違い
「ですます調」と「である調」の大きな違いは以下のとおり。
- 「ですます調」は丁寧で親しみやすい
- 「である調」は断定的で説得力がある
以下、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。
「ですます調」は読者に丁寧な印象を与える
「ですます調」は敬体とも呼ばれ、以下のような特徴があります。
- 読者に丁寧な印象を与える
- 誰もが親しみやすい
- 語尾が単調になりがち
丁寧な印象の文章を書けるのが大きな特徴で、ブログやアフィリエイトサイト、企業サイトなどの記事を書く際に多く採用されます。
年齢や性別に関係なく親しみやすいため、記事内容さえよければ多くのファンを獲得できるでしょう。
ただ、語尾のバリエーションが少ないため、単調な文章にならないよう注意が必要です。
- です
- ます
- でしょう
- でした
- ました
- ください
など、複数の語尾を使ってリズムのよい文章を書きましょう。
「である調」は読者に断定的な印象を与える
「である調」は常体とも呼ばれ、以下のような特徴があります。
- 読者に断定的な印象を与える
- 説得力のある文章になる
- 語尾のバリエーションが多い
- 上から目線になってしまう可能性もある
断定的で説得力のある文章を書けるのが大きな特徴で、論文や新聞記事を書く際に採用されるケースが多いでしょう。
また、「ですます調」と比べると語尾のバリエーションが多いため、リズムのよい文章を書きやすいといえます。
ただ、読者に堅い印象を与えたり、上から目線になってしまったりする可能性もあるため、ブログや商品紹介の文章で使うことはあまりありません。
「ですます調」と「である調」の使い分けを例文で解説
ここでは、「ですます調」と「である調」を使い分けるポイントを解説します。
どちらの文体を使うべきか悩むときは、参考にしてください。
1.企業サイトは「ですます調」で書く
企業サイトの文章は、「ですます調」で書くのが一般的です。
たとえば、次のような企業紹介の文章を読んでみてください。
読みやすく、親しみやすいですよね。読者の好感度がアップすることや、ファンが増えることなども期待できるでしょう。
あえて、「である調」に書き直すと、以下のような文章になります。
意味はわかりますが、堅苦しく、親しみは感じられません。
「である調」で書くほうが企業のイメージに合う場合もあるかもしれませんが、上から目線にならないように注意しましょう。
- 飲食店
- クリニック
- メーカー
などのWebサイトにおいても、「ですます調」を使うのがおすすめです。
2.ブログやアフィリエイトサイトは「ですます調」で書く
- 不特定多数の人が読むブログ
- 多くの読者の獲得を目指しているアフィリエイトサイト
などの文章も「ですます調」で書くほうがよいでしょう。
とくに、説明的な文章や商品をおすすめする記事は、「ですます調」のほうが読みやすく、読了してもらえる可能性も高まります。
次の例文を読んでみてください。
わかりやすく丁寧に説明してくれている印象を受けますよね。
一方、「である調」で書くと、以下のようになります。
上から目線で説明されている印象もあり、おすすめしたい気持ちも伝わってきませんよね。
やはり「ですます調」で丁寧に説明し、読者の信頼や好感を得るほうがよいでしょう。
もちろん、個人の日記的なブログの場合は、どちらの文体でもOKです。
3.論文は「である調」で書く
論文や新聞記事などは、「である調」で書くほうがよいでしょう。
たとえば、次の文章を読んでみてください。
断定的で力強い印象を受けますよね。
あえて「ですます調」で書くと以下のようになります。
丁寧な説明文ではありますが、論文のイメージからは離れてしまいました。
論文や新聞記事のように説得力が必要な場合は、「である調」のほうが適切でしょう。
ただ、研究や論文をもとにした解説記事を書く場合は、「ですます調」でも問題ありません。
「ですます調」と「である調」は混在してもOK?
「ですます調」と「である調」は混在させないのが基本ですが、例外もあります。
以下、詳しく解説していきますので、参考にしてください。
「ですます調」と「である調」は混在させないのが基本
「ですます調」と「である調」は混在させず、どちらかに統一するのが基本です。
混在させると、次のような素人っぽい文章になってしまいます。
統一感がなく、リズムもよくないですよね。
ここでは、以下のように「ですます調」に統一してみます。
「ですます調」と「である調」を混在させてもよい3つのパターン
以下3つの部分においては、「ですます調」と「である調」を混在させても問題ありません。
- 箇条書きの部分
- セリフの部分
- あえて混在させる部分
それぞれ例文で確認してみましょう。
箇条書きの部分
箇条書きの部分のみ「である調」ですが、違和感はありません。
セリフの部分
セリフの部分だけ「である調」ですが、不自然ではないですよね。
以下のように、セリフの部分だけ「ですます調」にしてもOKです。
あえて混在させる部分
全体としては「ですます調」ですが、「郷土料理を食べる…。」の部分だけ「である調」になっています。
ただ、とくに違和感はありませんし、深みのある文章ともいえるでしょう。
「ですます調」と「である調」を使い分けて読みやすい文章を書こう!
今回は、「ですます調」と「である調」の違いや使い分けのポイントについて解説しました。
語尾が異なると、文章全体の印象も大きく変わりますので、メディアやターゲット層に合わせて適切な文体を選びましょう。
企業サイトや個人ブログなどにおいては、「ですます調」を用いるのが一般的ですが、語尾が単調になりがちなため注意が必要です。
以下の記事では、10の語尾を使い分けて文章のリズムをよくするコツを紹介していますので、あわせて読んでみてください。